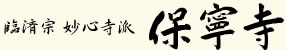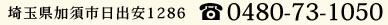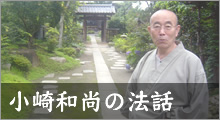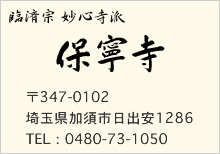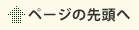泣けて困る
昭和二十年終戦の前年、十九年四月の生まれである。日本中は極貧の中にあった。
大阪、道頓堀で家を焼かれた一家六人は、両親の里の親戚を頼っての流浪の旅が始まった。
日本中の多くの家族、特に都市部の空襲で壊滅的被害を被った人々は大なり小なり
同じような辛酸をなめながらの戦後であったろう。
ひもじくてびーびい泣いていたのであろうが、私はほとんど記憶にはない。当時誰もが
背負った苦難ではあったし、生活が楽になっていく様子は、子供心にも、実感できたし、
父親が働いていた神戸に移ってからの生活水準の向上は、目覚ましいものがあった。
裸一貫のスタートであるから極貧生活であったことには変わりはないが、日に日に、年々
向上の様は、自分が働いて、稼いで良くなっているのかと錯覚するばかりであった。
終戦直前に生まれて、大きな混乱期の真只中にも拘わらず、ぼんやりと問題意識の
深さもなく、言ってみれば至って平凡に育って今日に至っている。
之を喜こぶべきか、悲しむべきか?
わが身を顧みるに、偉丈夫の仁でも無かったし、さりとて女々しき仁でも無かったようだ。
ところが、最近は、年を取ったせいか、やけに涙もろい。
松本清張の「砂の器」にやたら泣けるのである。
加藤 嘉(ただし)演ずるハンセン病者木浦千代吉とその息子が、業病からの快復を
頼んで行脚に出るのであるが、その病故、いわば、村追放という当時の認識であった。
小説の主題、殺人事件解明のバックにある、昭和という時代に翻弄された人々の悲哀、
村八分、差別は今尚日本人の心の中に遺伝子として残っているのでは無いでしょうか?
因みに業病とは、生前からの悪いおこないの報いとしてかかるとされた治りにくく、
つらい病気。とありました。
極寒の日本海や雪原を一途に行脚する本浦親子を想う度々、もう泣けて泣けて。
なんという映画力でしょうか!
この描写は、小説だと四~五頁でしたが、なんと、映画は四~五十分の頑張りです。
僅か6~7歳の子供と業病を背負った親子が家々を訪ねて悲しく無慈悲なる無心の托鉢。
「上求菩提、下化衆生」などと闊歩しながらの修行僧(雲水)のそれとなんと次元の
異なることか。修行に命がけになれなかったどこかのお寺の坊様は唯泣くばかりです。
それともう一つ。それは「戦友」です。
「ここはお国の何百里、離れて遠き・・・・・」 もう、うるうるです。
「時計ばかりがコチコチと・・・」 もういけません。涙と鼻汁で歌えないのです
わたしの身の回りには戦死したり、引揚げ者で辛い思いの人もいません。
どうしてこんなに泣けるのでしょう?