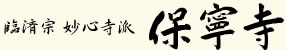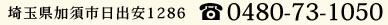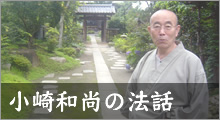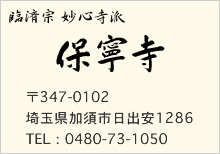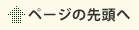江戸末期、慶応から昭和二十数年までを生きた山本玄峰という和尚がいた。
近代の傑僧と言われた方で、私が得度を受けて修行に出たのが昭和四十二、三年だったが、玄峰和尚はその二十年も前に遷化(死亡)されています。
その名声は禅宗界だけでなく世間にあっても知られています。先の戦争終結の緊張時には、無血開城時の勝海舟や山岡鉄舟のような役割を担っておられます。坊さんになる前、目を悪くし、回復を願って、四国遍路を連続七回もされたのだが、其のかいもなく、目は一向に良くなりませんでしたが、縁あって、四国遍路寺では珍しい禅宗、雪渓寺の和尚との縁を得て、その弟子になり、やがて修行に出ます。教育もなくその上目も見えないし自分のことも皆目分からない前途多難の旅立ちで、先行き真っ暗な出立でありました。「只、一心に修行するならば、たとえお前の目は見えずとも、心の目は必ず開くであろう」和尚のこの一言だけが光であったのです。その修行は、壮絶の一語。他の追従を許さぬものであり、今となっては垣間見ることもできませんが、残された回想録を読むにつけても、道を求める純一さに驚愕し、そして、畏敬の念を禁じえません。
やがて、神仏の加護もあってか目も徐々に回復し、大きな悟りの体験あって、心の目も見えるようになりました。それからの玄峰和尚の弟子達への叱咤激励は、「人のために為せ」、「陰徳を積め」でありました。
大慧禅師発願文の中に「七日以前に、予め死の至らんことを知って、安住正念、末後自在に、この身を捨て終わって、速やかに仏土に生じ、面のあたり諸仏に見(ま)みえ、正覚の記を受け、法界に分身して、遍く衆生を度せんことを」とありますが、ご自分の死の至らんこと知って、十日前から食を断って、十日後、多くの弟子達の祈りの中、粛々と遷化されました。悟りの最終眼目、「法界に分身して、遍く衆生を度せんことを」の確信を念じつつ。
それにつけても、保寧寺先住、熊田応其和尚の事であります。和尚遷化の後、出版致しました「黄泉の国からの怪文」でも披露いたしましたが、この和尚も同じように十日以前に死の至らんことを知って、絶食に入られました。厳命故、如何とも仕方無く動向伺に朝課後、ご挨拶にいって生死の確認だけの十日間でありました。何人をも一切、部屋の出入りを許しませんでした。果たして十日目の朝にはご返事なく、ご遷化を知りました。後住一人の見送りという寂しいものでした。熊田和尚の心境や如何に❓
物心両面に亘っての「孤高の人」という言葉を地でいった和尚でした。
私もそんな事は他人事と現を抜かして居れぬような年恰好になったものの、先人和尚を追従するには心身の気力欠落はあきらか故、きょう一日、今日一日、出来ることを粛々と、といった近況です。
皆様におかれましてもこの様な不安定状態の中でこそ一日、一日を大切に心静かにお過ごしください。只、祈るばかりです。