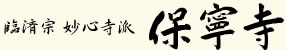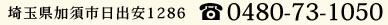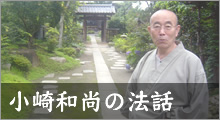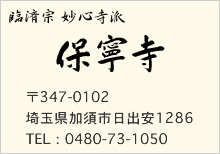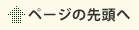バシー海峡は台湾島南端からフイリピンのルソン島間のルソン海峡のうち、台湾側ガランピ岬とフイリピン諸島との間にある海峡のことを言いますが、私たちの言うバシー海峡は、もっと広域を言います。即ち、第二次大戦末期、ほとんど無力化していた日本軍は、なをも最終決戦に挑み、結果、ことごとく米潜水艦の魚雷砲で沈められていった輸送船の悲しい海峡、その悲しい場所を総称して、バシー海峡と言います。撃沈され、沈んでいったすべての場所を、バシーという悲しげな音の響きから総称したのでしょう。
撃沈されて海の藻屑となった慟哭の命は少なくとも十万人を下らないといわれています。1944年から1945年にかけてのことです。このことから、魔の海峡 とも、輸送船の墓場ともいつしか呼ばれるようになりました。
そのうちの一艘の輸送船、「玉津丸」の通信兵、中嶋秀次さんは、十二日間の漂流の後、たった一人生き残ったのです。しかも、この輸送途上の「戦死者」は大規模な慰霊祭の行われることもなく、「忘れ去られた戦没者」となっていたのです。
中嶋さんは戦後、むねんのなみだを呑んで散っていった戦友たちの慰霊のため、私財をなげうって、戦後36年を経た1981年、バシー海峡を見下ろす地に、鎮魂の寺、「潮音寺」を建てました。中島さんは数年前に亡くなられましたが、戦後70年を経た、今年8月2日、日本から、160人の関係者の慰霊の訪問となりました。このことは、NHKでも取り上げていたので、ごらんの方もあると思います。
私たちは、僧俗合わせて二十五人の慰霊ではありましたが、現地の篤く、親切な引きまわしによって、厳粛に慰霊供養を行いました。あらん限りの鎮魂の気持ちを込めて、献笛が出来、無念の霊魂の慰めになったかと、少しばかりの安堵を頂きました。
ものすごい雨の中、ガランピ岬につきました。運よく雨も上がり浜辺に着きますと、そこは楽しげな海水浴場。70年前の慟哭の海を偲ぶにはあまりに明るく、僧服の我々が浮いて見えるほどでしたが、岬突端の岩場は険しく皆は行けないので、私一人岬の先端、波打ち際まで行きまして、またも献笛と相成りました。英霊たちはきっと喜ばれたと信じます。
翌日、三十日は台中地区の光徳寺で盂蘭盆会斎会が行われました。生憎の雨でしたが、参道までの道中、信者さんは自分たちはずぶ濡れになりながら傘のトンネルを作ってくださり、お経を唱えながらのお出迎えです。
台中南部の合同盂蘭盆会です。お坊さんの数、300人ぐらいでしょうか?その内尼さんは、半分ぐらいでした。一般信者さんの参列、加担も合わせると二千人は下らない参集です。この方々が、先導のお経に合わせて朗朗と唱えての斎会の始まりです。儀式の終わるころには、円形机の上には斎会のご馳走がいっぱいです。式中には信者さんが喜捨のお布施を恭しくお持ちくださり、有り難くも、勿体ない思いで戴くばかりです。
此の光徳寺は妙心寺派の別院の様な位置に在って、本堂は準日本式で、ほっとする空間でした。雨の中、開山塔へも伺って、大悲呪一巻。
忙しい旅ではありましたが、思い深き有益の旅でした。
終戦60年の年にも中国全土の禅宗寺院で平和祈願の旅を則竹老師と行ってまいりました。其の平和祈願を反芻しながらの帰路の人となりました。