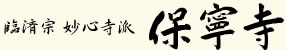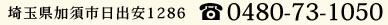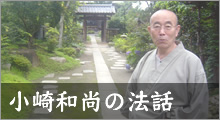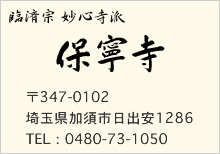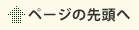音と言っても色々有るが、巡礼者にとって、一番敏感なのが、宿泊先での音で有る。この国の町や村は、他のヨーロッパの街(キリスト教文化圏)と同様、教会を中心に出来上がっている。教会を中心に放射線状や、回廊式に町や村が出来上がっているわけだが、全体として、道は非常に狭くて混みっている。建物は殆どが石作りである。そんな訳で音が非常に響く。教会前の広場は町の中心で、言って見れば大社交場で喧騒の中心でも有る。アルベルゲは殆どが教会の周りにあるわけだから矢張り喧騒の中に有る。夜の十二時ぐらいは我慢もできるが、夜中の二時、三時までと喧騒は続く。村はどうかと言うと、思わぬ伏兵が有った。教会である。朝と言わず夜と言わず兎に角なり続けるのだ。例よってアルベルゲは教会の真下にあるものだから、突然鳴り響く余り質の良くない鐘が無闇やたらに響くのだ。保寧寺の鐘が懐かしい。教会の鐘は大体が一時間おきだが中間の半にも鳴るが、数日前に泊まったアルベルゲの教会はなんと、十五分おきである。二十四時間十五分おきに鳴り響いている。恐ろしいことだ。神戸の六甲川をはさんで祥龍寺と六甲教会が有ったが、朝の大鐘と教会の鐘はうるさいと言うことで敢え無く中止となった。悲しいことである。昨日泊まったアルベルゲは果たして三十分おき。妥当であろう。がしかし、この日は日曜日。村の祭りときた。覚悟で床に着いたが、えらいことですわあ。何とスピーカーの大音響と大喧騒は、我々出立の朝六時まだ延々と続きました。信じられないことです。広場を通って行くと高校生ぐらいでしょう、朝まで飲み歌いまくった女の子が網代傘の私に飛びついて来る、交代に飛びついて写真を撮りまくる。新学期前の最後のハチャメチャか?なんとも凄まじい。凄まじい音のご披露でビックリでしょうね。しかし、この難所を過ぎれば、ペリグルム(巡礼者)の出入りと、挨拶はあるものの、ひたすら歩き、心の沈黙の世界に浸ります。出入りの息音、ザックザックの靴音ぐらいが音と言えば音でしょうか?沈黙の音の深みを得るための反作用としての喧騒の試練なのかもしれません。