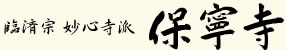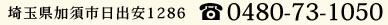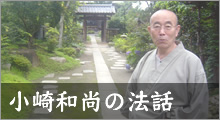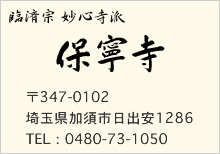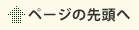坊さんは聖職者ではなく僧職者(職業人)になさり下がったという話。
その昔、坊さんは出家者としての家を出る(全てを捨てる)ことによって全てを得る修行者としての生きる信仰の証としての存在者であったが、今日は、真逆の存在者としての立ち位置であることを自他ともに認めている存在者となった。かって40代の頃か、スペイン、フランスのカソリック、ベネディクト派の修道院で過ごすことがあった。修道生活費は沈黙を護る(祈りの生活ー神のみ心、宇宙の真理を知る)ことが生活の第一義であった。左様なわけで深く修道者と会話による関わりを持ったわけではないが、その修道生活における一つ一つの所作から修道の深さを垣間見るしか無かったのであるが、基本は、修道士の心がどこまで神の御心に向かっているかどうかである。修道院の生活は禅宗の僧堂生活と似かよっっている。日本の禅宗僧堂体験者としては修道生活の本質は理解できる。スペイン フランシスコ ザビエルが生まれたハビエル城のあるレイレの修道院でバスク地方出身のノビシア(修道者となるための修練期間者)と一緒した事があった。他の修道者と同じ様に生活を重ねて行くうちに修道士しての自覚を確かめて行くのである。最低5年はかかる。晴れて修道士となっても尚9年の試練を得て最終誓願の後、この身の全身全霊を神のみ心に捧げる結定となる。ここ迄の道行の基本は祈り(神さまに近づきたい)の継続が続く集中力と持続力のみである。我々禅宗人にとって、祈り(仏様に近づきたい)の継続と集中力とは何ぞ?
坐禅の継続しかない。
今の老師方はどう言っているのかしらないが、わたしの僧堂時代の老師がたは、「座れ、座れ 座ってなんぼじゃ」と口を酸っぱくして説いておられた。今思っても有難い教えであった。それと、陰徳の行の大切さを解かれた。陰徳の行は隠しても隠しても自然とその人の立ち振舞いに現れる。反対に徳のない人のそれには何を為しても徳の香りがない。嫌らしさが残るのみである。かくしても徳の徳たる所以の凄みか?坐禅の継続は徳の完成にある。修行の甲斐あって徳を得たとしても、坐禅の継続なしには続かない。徳まだ薄き人はその到来を信じて一心に座るのが肝要である。今、スペイン北部地区、ガリシアのカカベロスのアナという人の家にいる。10数年前の聖地巡礼の時、この地ですっかり疲れはてて動けなくなった。ここで出会った当時25〜6歳のアナと言うマッサージ師が彼女であった。まだ初心者で上手くはなかったが彼女の治したい、私の治りたいという祈りにも近い願望が治療の成功を見た様な気がする。その彼女が今はこの地で鍼灸治療の先生として活躍している。お伝えしたいのは、旦那様と一緒に街の同志と坐禅を楽しんでいることである。いのりの生活を楽しんでいる。今日の日本人と言えば、祈りという言葉の認識はわずかに法事や亡くなった身内の極楽浄土の安楽を願うのみの祈りの認識である。鑑みるに僧職者に於いてもこの認識はあまり変わらな様である。他人様より少しはお経なども読んでいるかも知れない。当たり前である。残念な事にそのお経は彼らの商売道具でる。宗教教団に身を置く坊主の1人の私がこ様な悪口を書いてしまうなんて、涙も出ないほど情けない。稼がないお経を読めとは、かっての老師がたの常套句であった。山本玄方老師然りである。時間がなくても寸暇を盗んで金剛経を読まれていたとか。だから徳行が生きるのである。生き仏様となるのである。廃物毀釈の真っ只中にあっても玄方老師が住まわれるとお寺が再建されたという話は誰もが知っている話である。真の出家者たる生き様であろう。何度も言って恐縮だが、数はまだまだ圧倒的に少ないがアメリカ、ヨーロッパ人達のその熱心に坐禅をする姿に接する度に、日本禅宗界の禅の神秘に対する認識の甘さには、呆れるばかりである。